雨水うすい
2月19日~3月4日
春が深まり、さまざまなものが動きはじめる時期です。
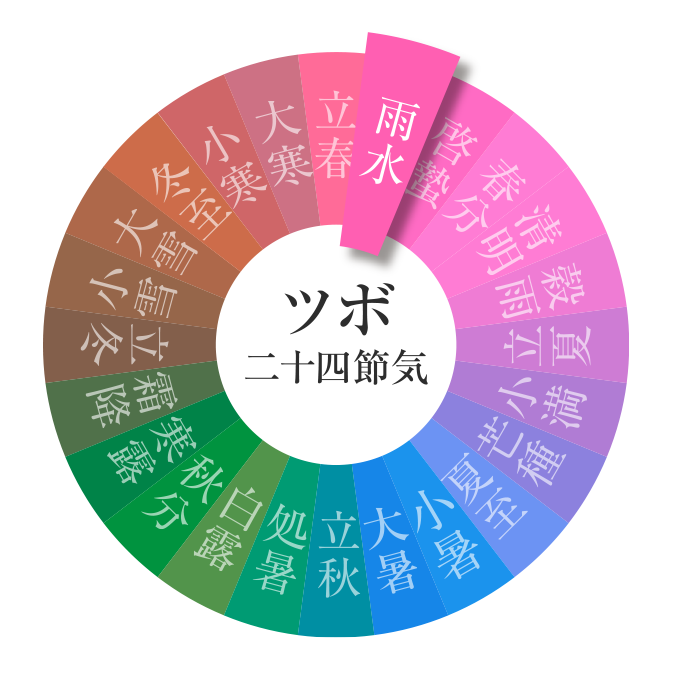
雨水の養生
- 雨水という季節
- 春を迎え、季節のうつり変わりや新しいできごとにも応じられるよう、心身ともに充実させために、「営気(えいき:豊富な栄養)」を養いましょう。
この時期、身体が季節の変化に応じられないと、全身の循環にとどこおりが起こりり、身体の隅々までエネルギーが行き届かなくなります。
そのため、手足の末端が冷えたり、ちょっとしたことで疲れたり、やる気がなくなったりします。
この時期は、心身ともにメンテナンスし、身体の隅々まで栄養が行き届くように、身体を温め、ほぐすことで、いつでも動ける準備をしておくことが大切です。
- 雨水の養生
- 雨水は、目の充血やむくみなど循環のトラブルが目立ちやすくなるため、むくんだ部位の筋肉をストレッチしたり、マッサージしたりするセルフケアが大切です。
特に循環の改善を目的とする場合には、1秒に1回程度、心拍数と同じ規則的なリズムで、筋肉をもんだり、マッサージしたりしましょう。
また、規則正しいリズムで歩き、全身の循環を良くすることも大切です。
ふくらはぎは第2の心臓とも呼ばれ、全身の循環を調整してくれます。歩くことは気分転換にもなるため、1日10分~15分でもよいので、心拍数に近いリズムで歩くこともおすすめです。
雨水のツボ

豊隆
ほうりゅう
ほうりゅう

- ツボの位置
- ひざのお皿のすぐ下にある外側のくぼみと、足首にある外くるぶしの最も高いポイントを結ぶ線を想定します。 その線の真ん中あたりが豊隆(ほうりゅう:ST40)です。

季節のサイン
季節の移り変わりを知らせるさまざまな変化。自然界からのサイン。

霞(かすみ)

芽吹き

春キャベツ

ハマグリ

トビウオ
季節の養生とは
私たちは、一年一年、めぐりくる季節の変化に身体をかさね合わせ、年輪のように歳を重ねていきます。季節に応じた生活、季節にあわせた暮らしを心がけることこそ、健康づくり、人生を豊かにする第一歩なのです。
年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。
年々、気候の変動が激しさを増しています。だからこそ、今の季節をゆったり味わう感性を持ちたいものです。古くから受け継がれてきた知恵を、今をしなやかに生きるための養生として、ぜひ生活にいかしてお楽しみください。

監修
伊藤 和憲 先生
鍼灸学博士
明治国際医療大学 鍼灸学部
鍼灸学科 教授
専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。
明治国際医療大学 鍼灸学部
鍼灸学科 教授
専門は「痛み」。NHKの健康番組などに出演。著書『今日からはじめる養生学』はじめ、痛みに関する専門書多数執筆。
おうち薬膳レシピ
二十四節気
春
夏
秋







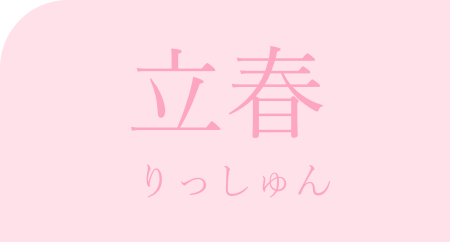
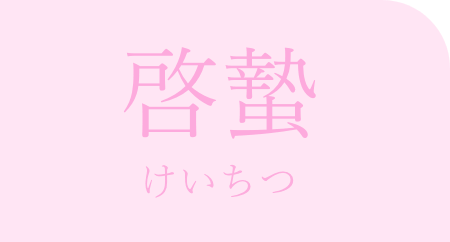



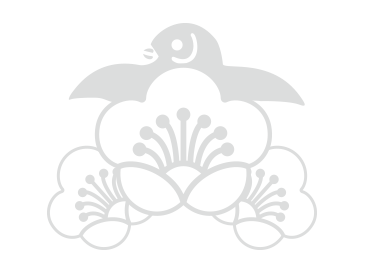
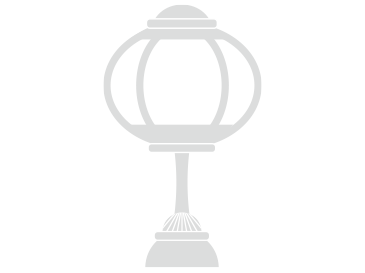

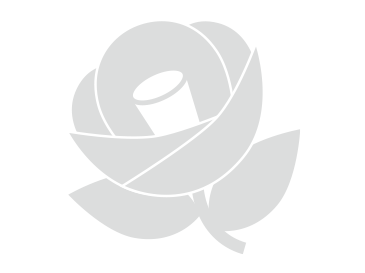
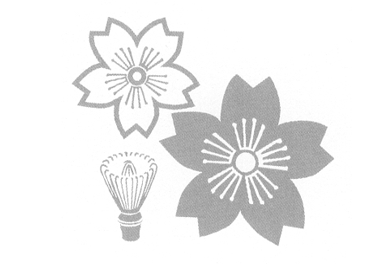
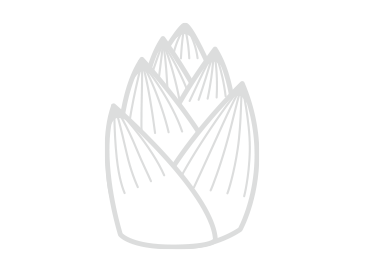
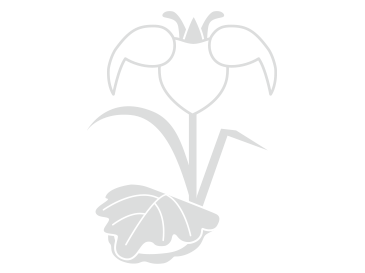
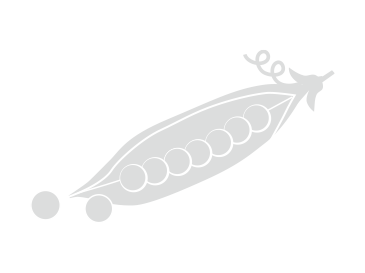
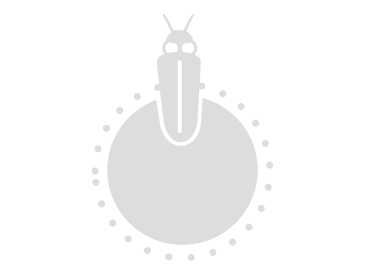
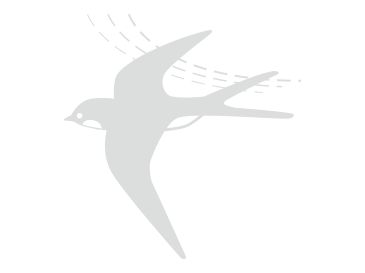
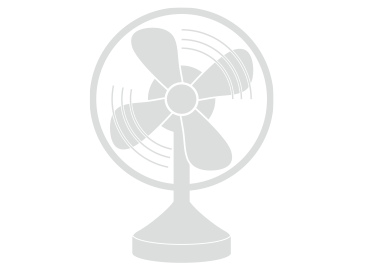

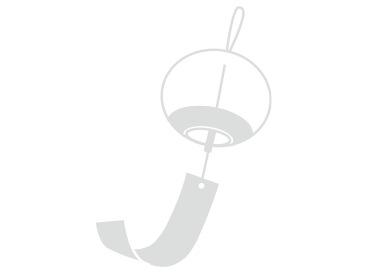
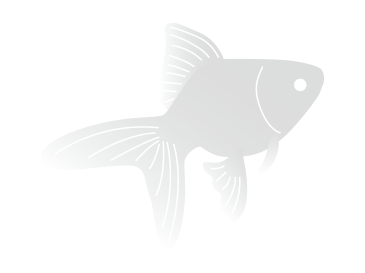
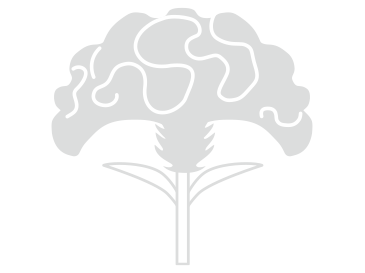

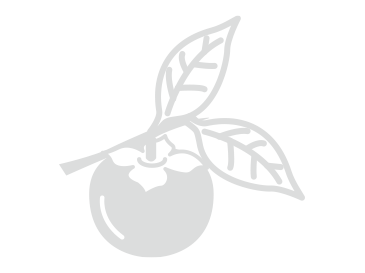
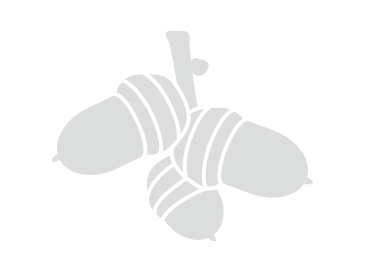
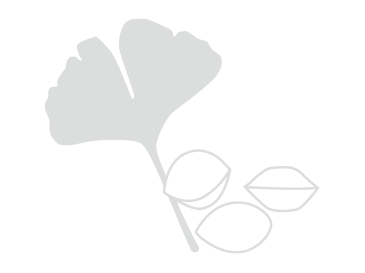

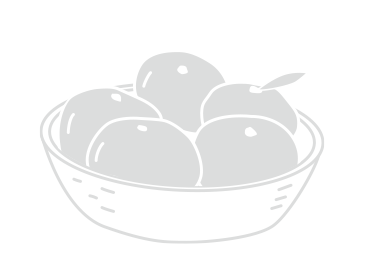


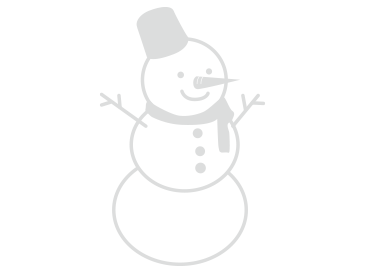
 ツボ
ツボ 季節の養生
季節の養生 年代別ケア
年代別ケア 薬膳
薬膳